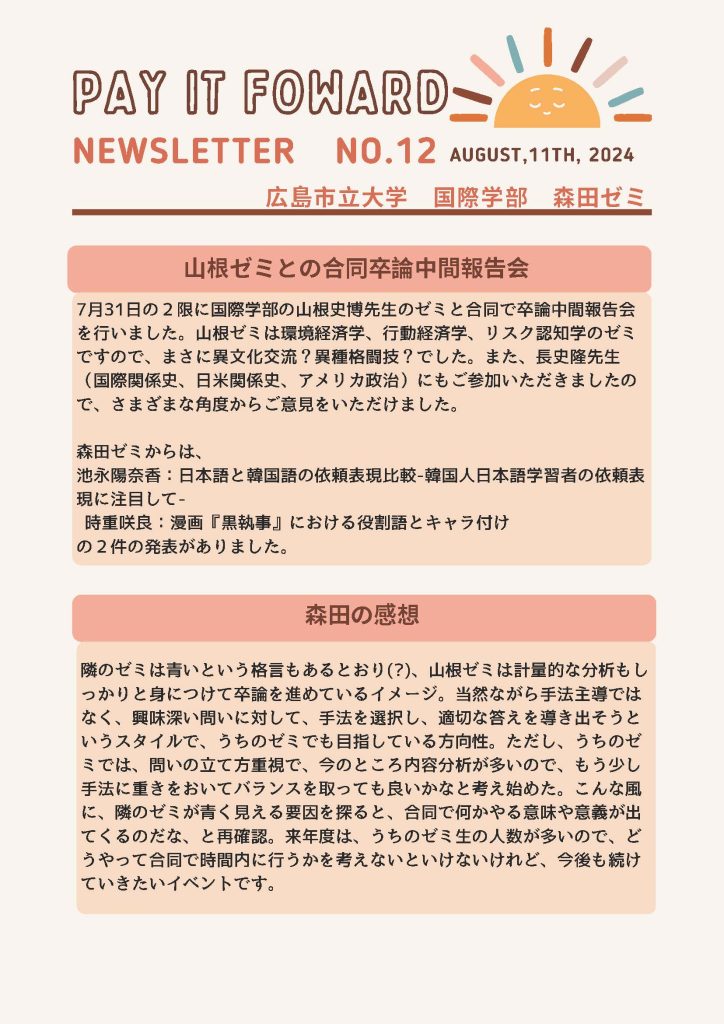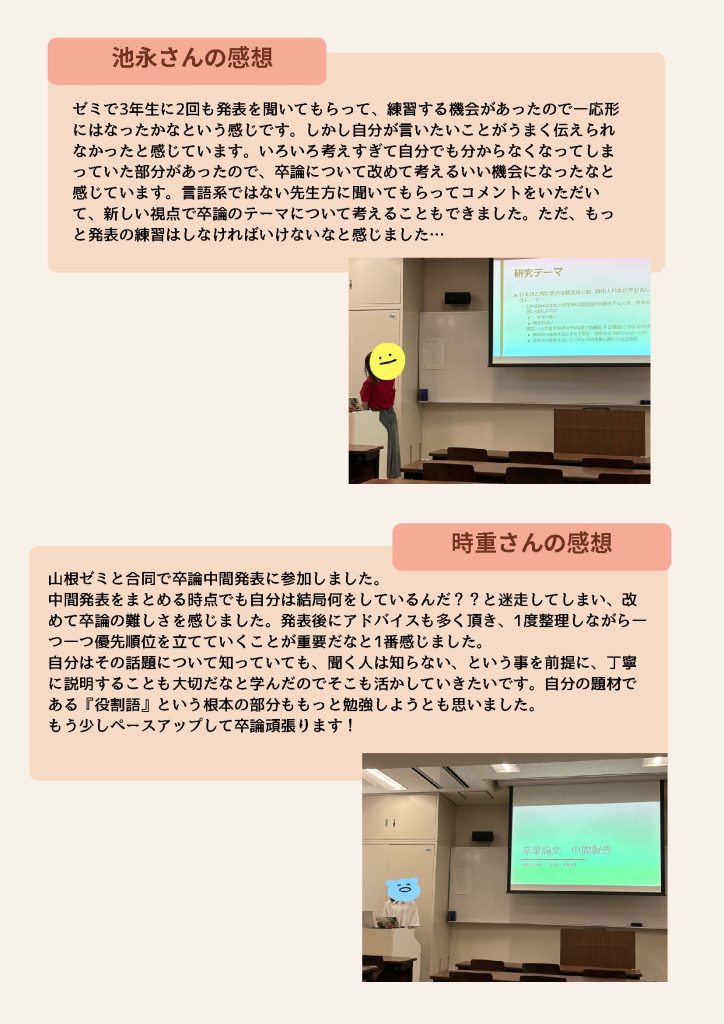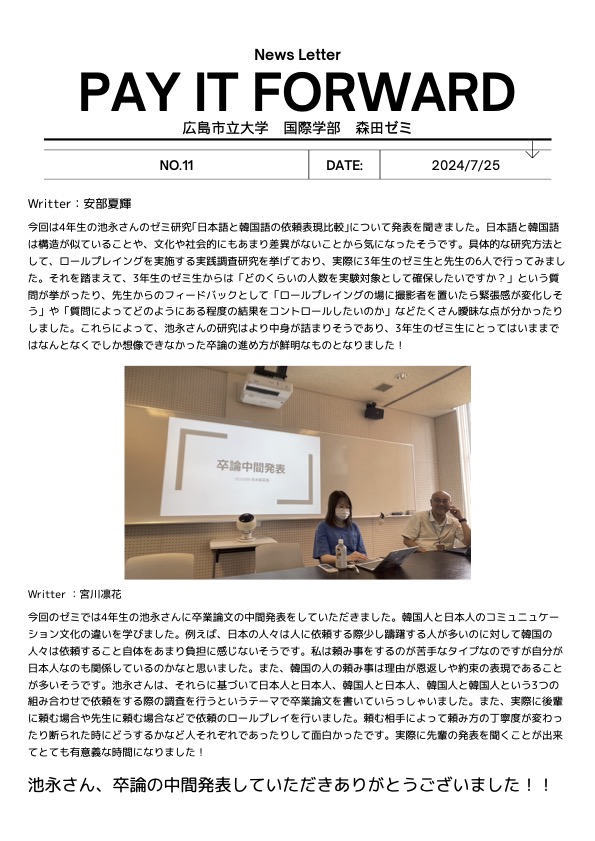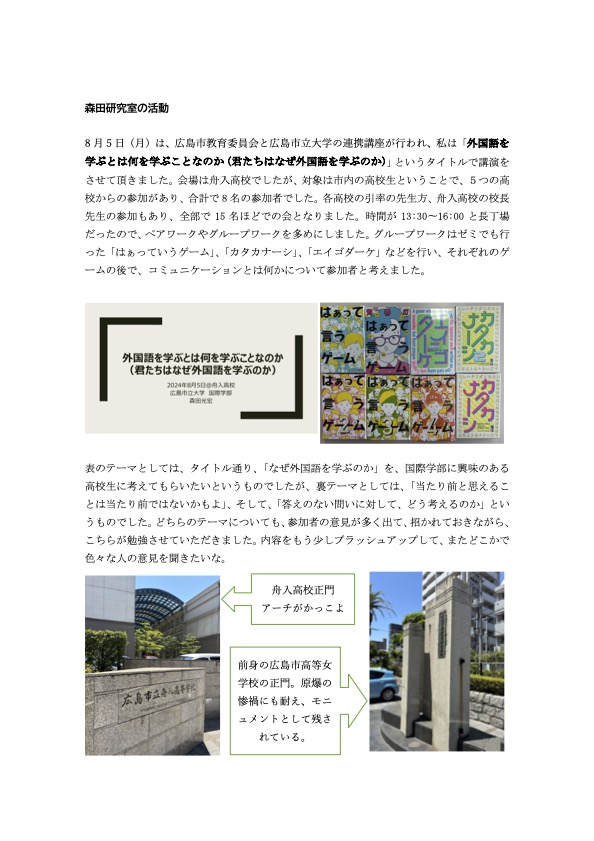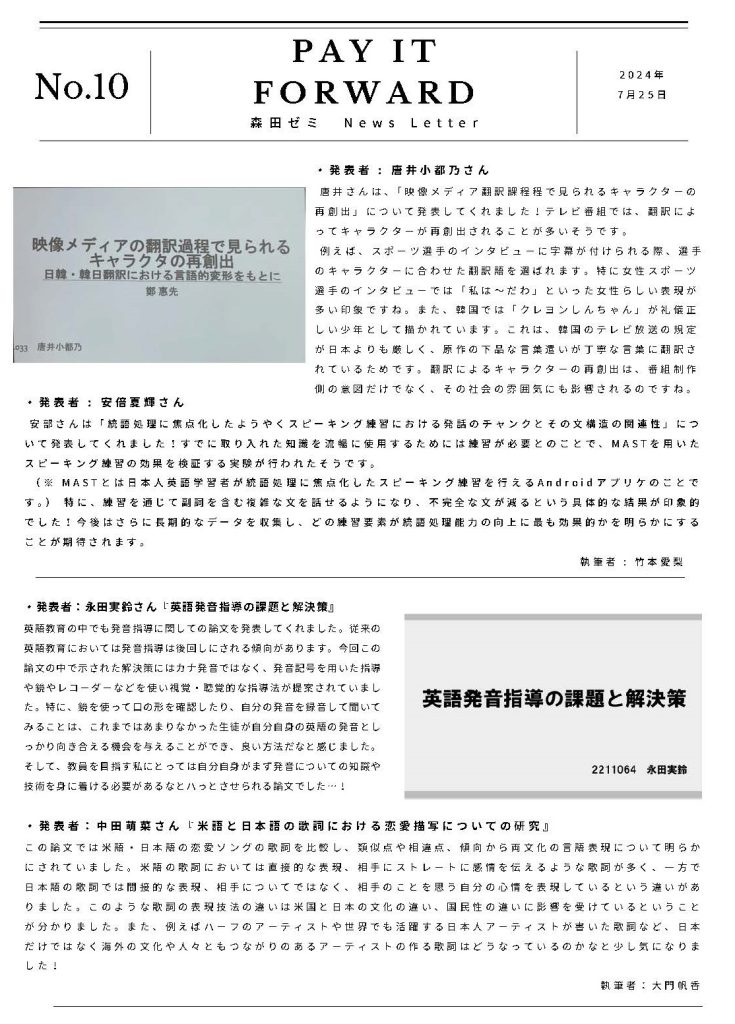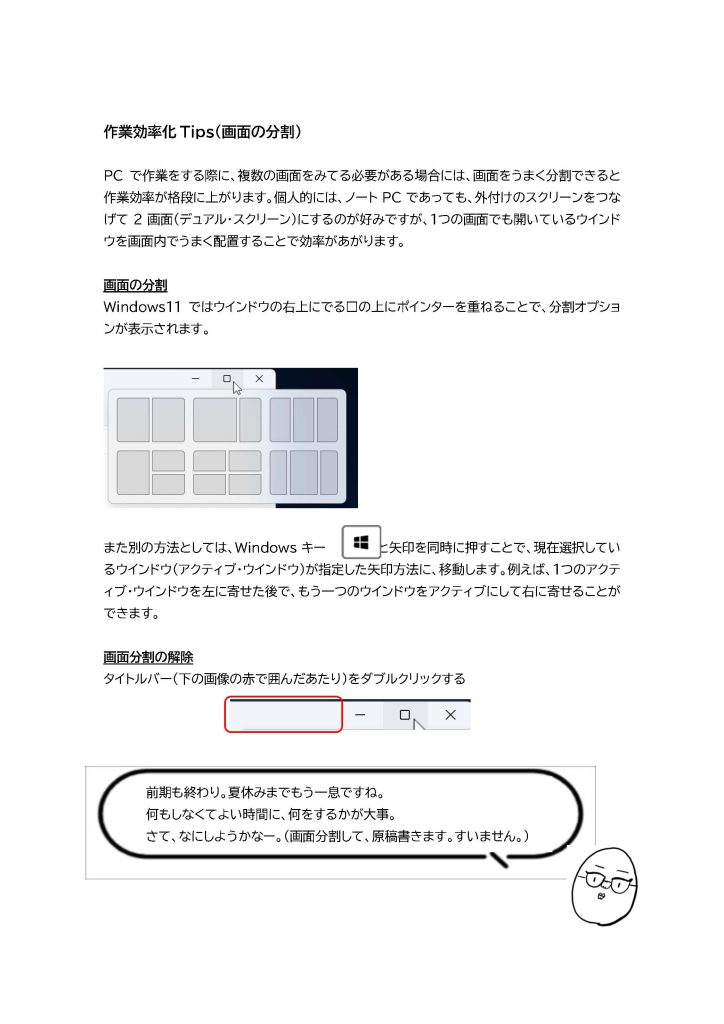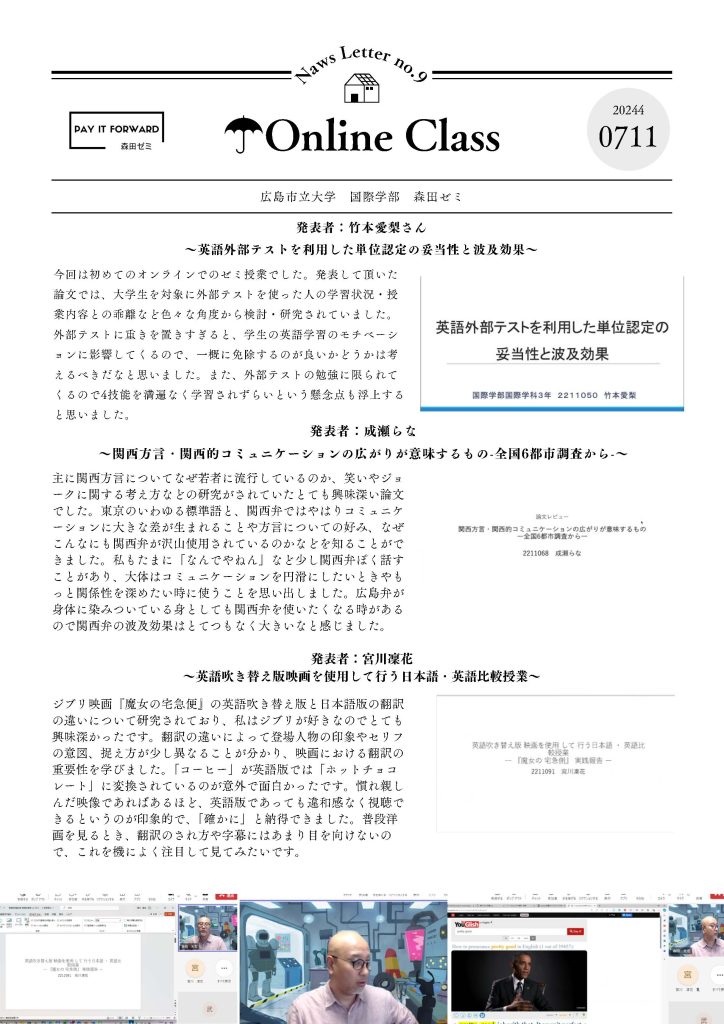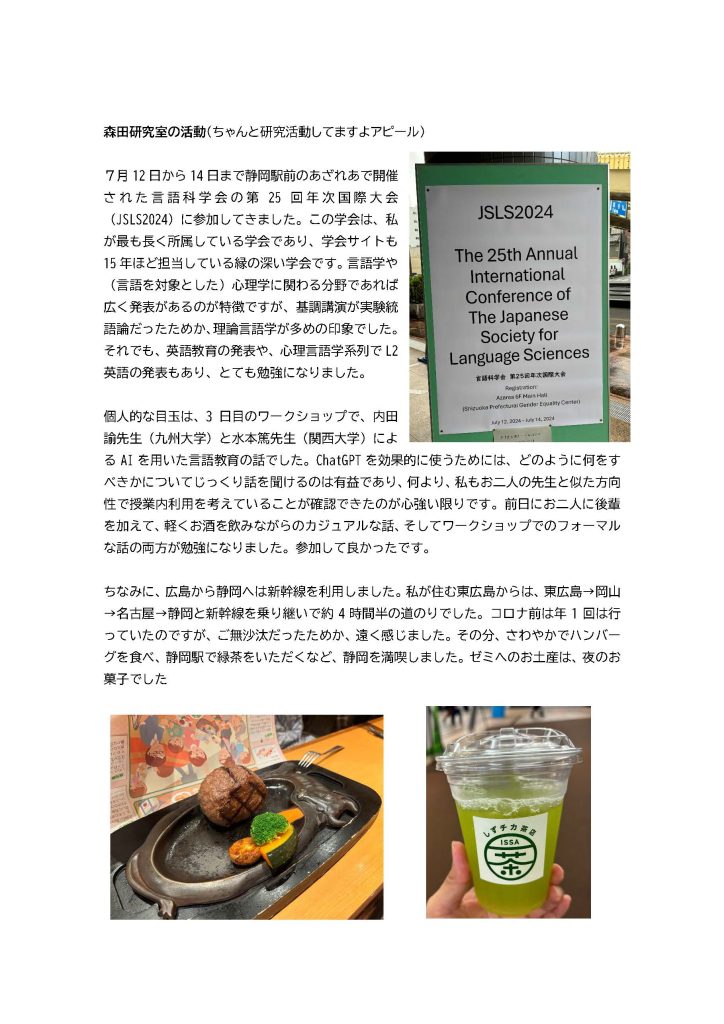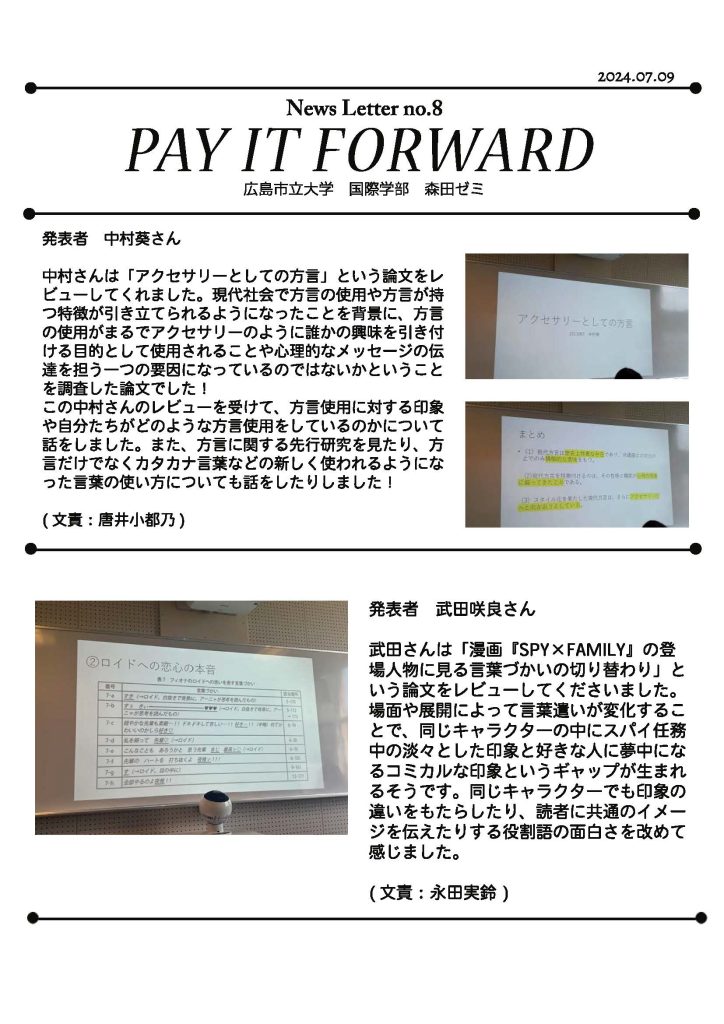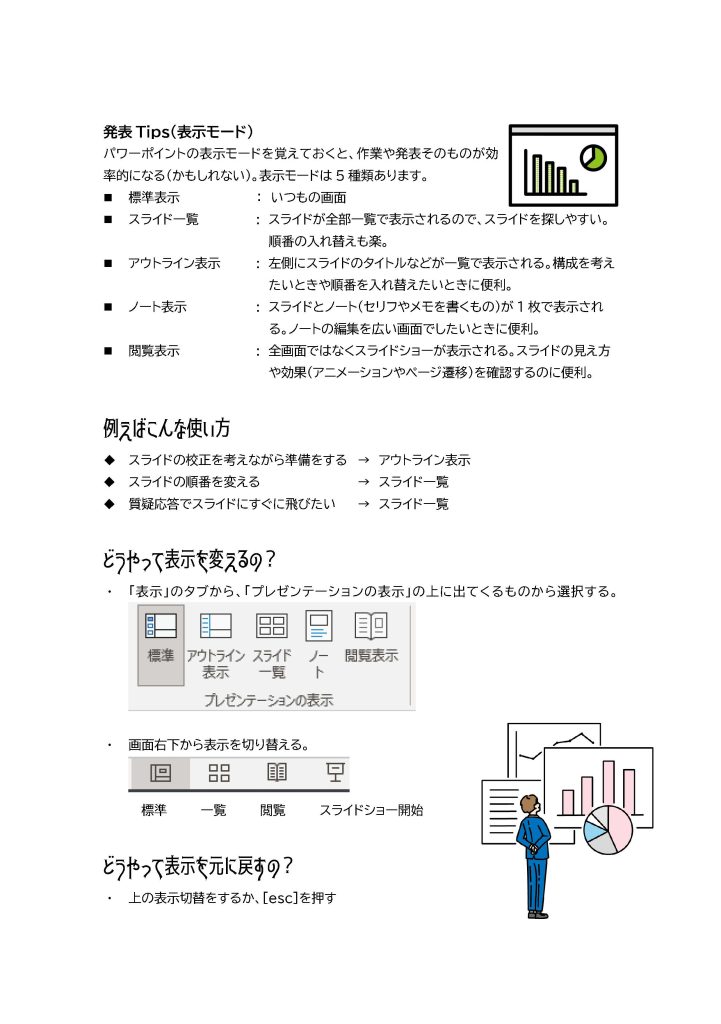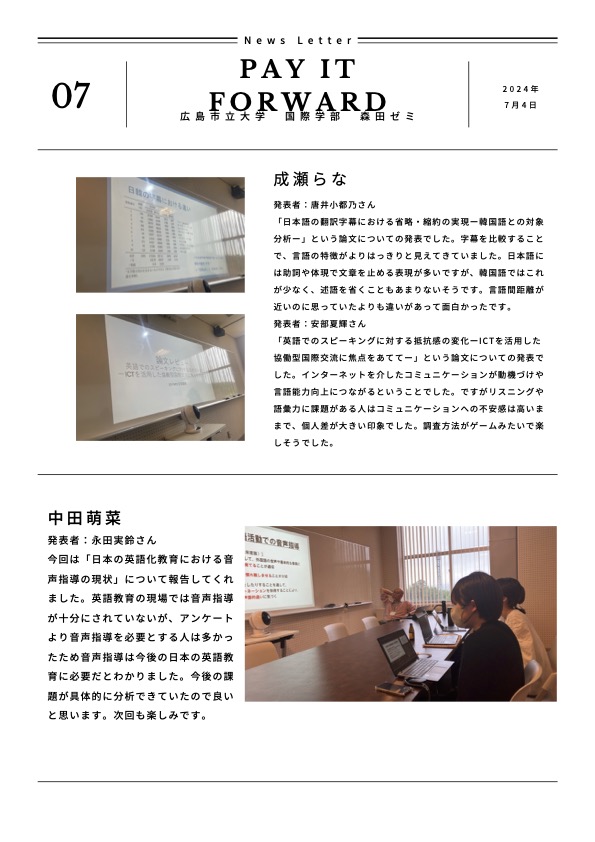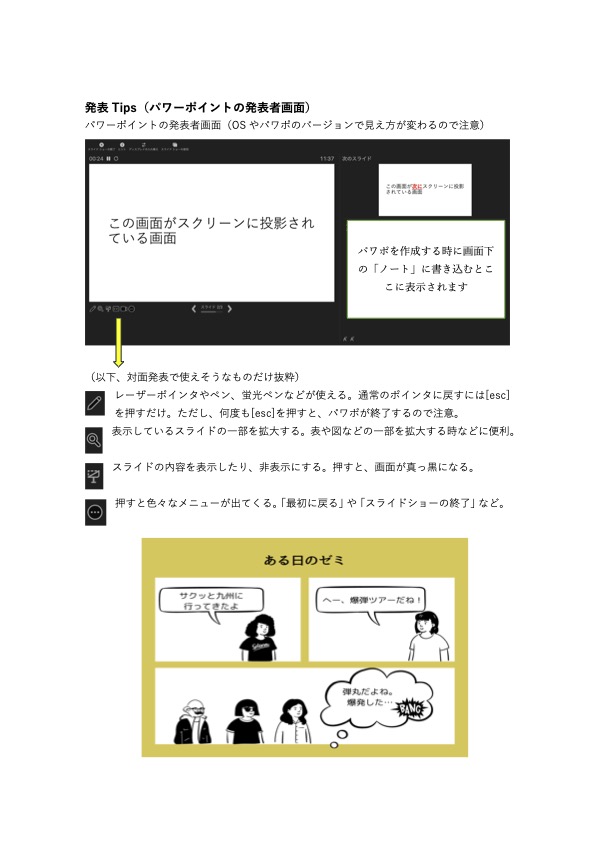森田ゼミNews Letter No.14
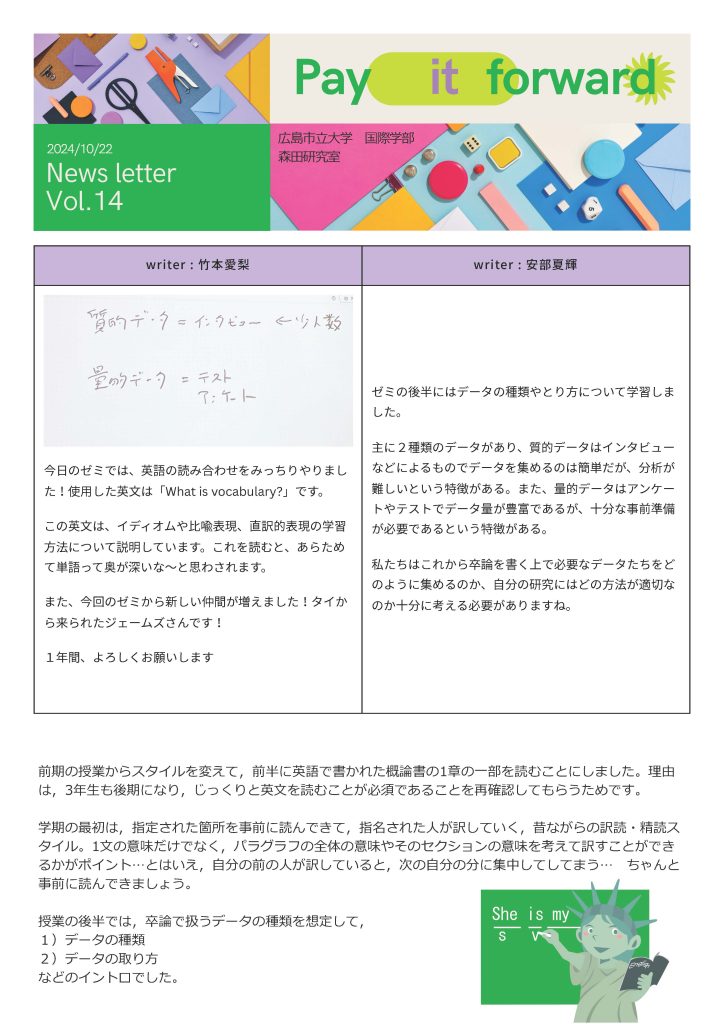
Morita Lab.
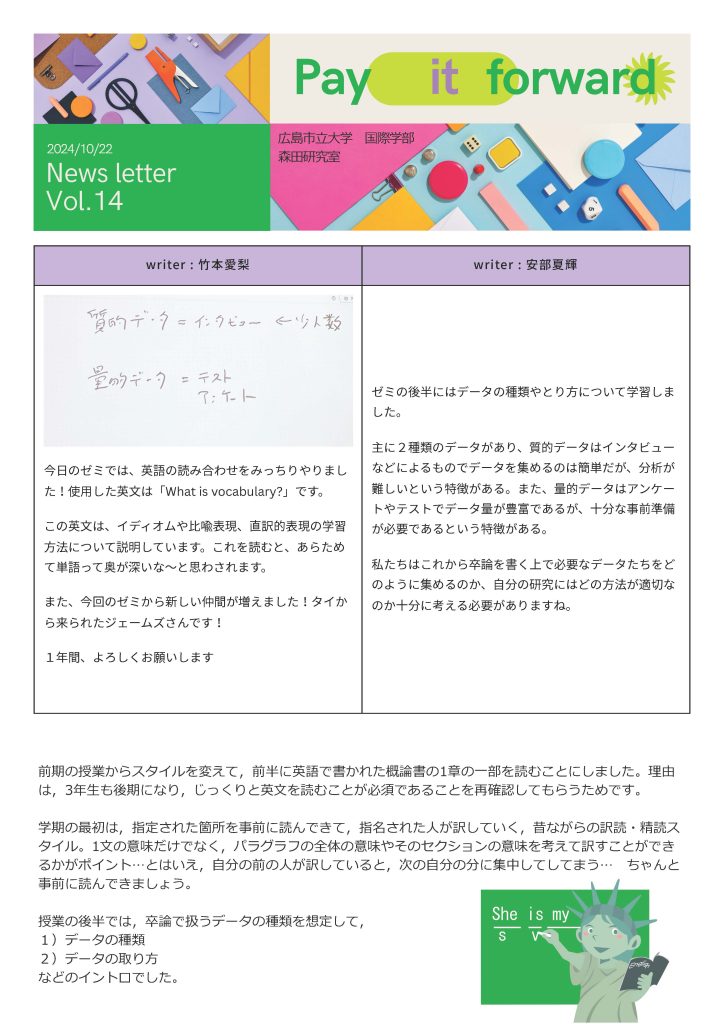
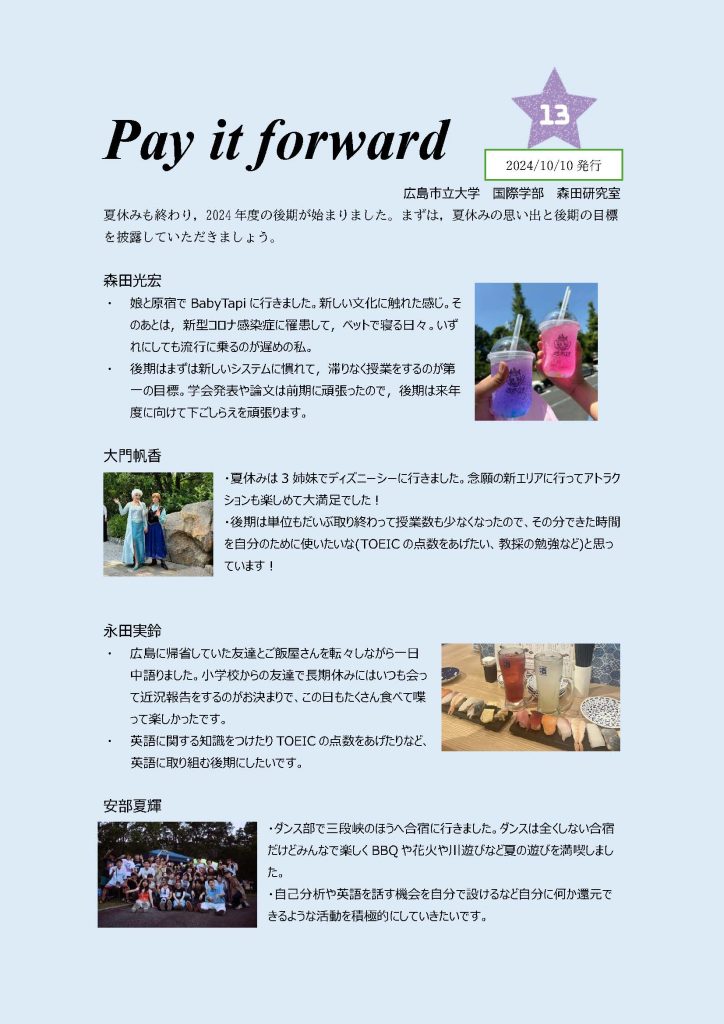
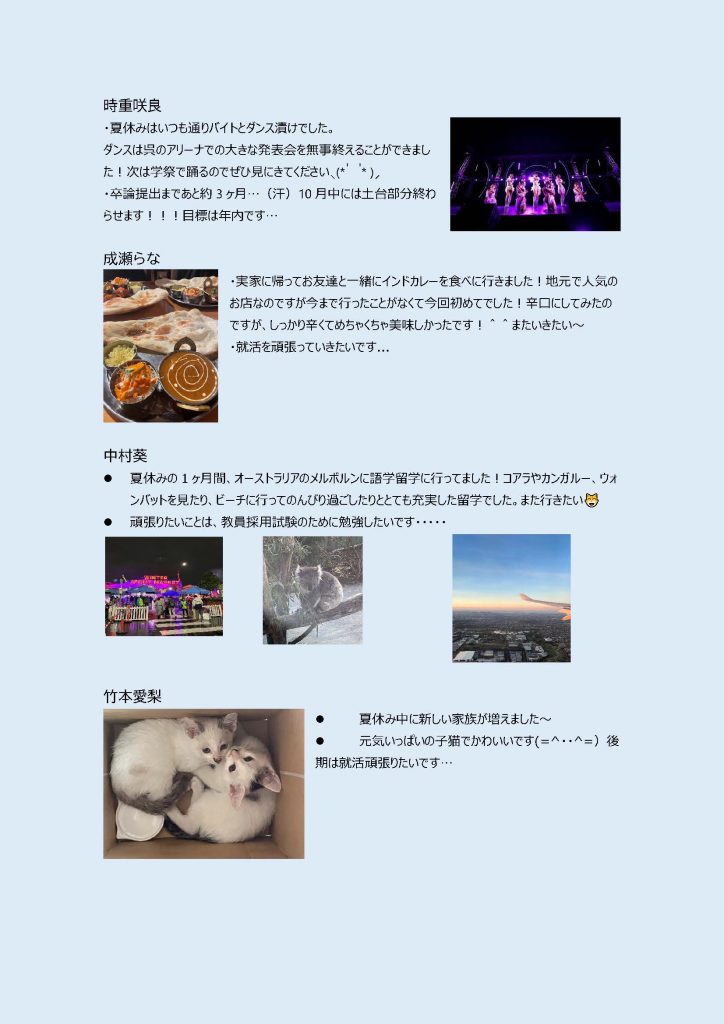
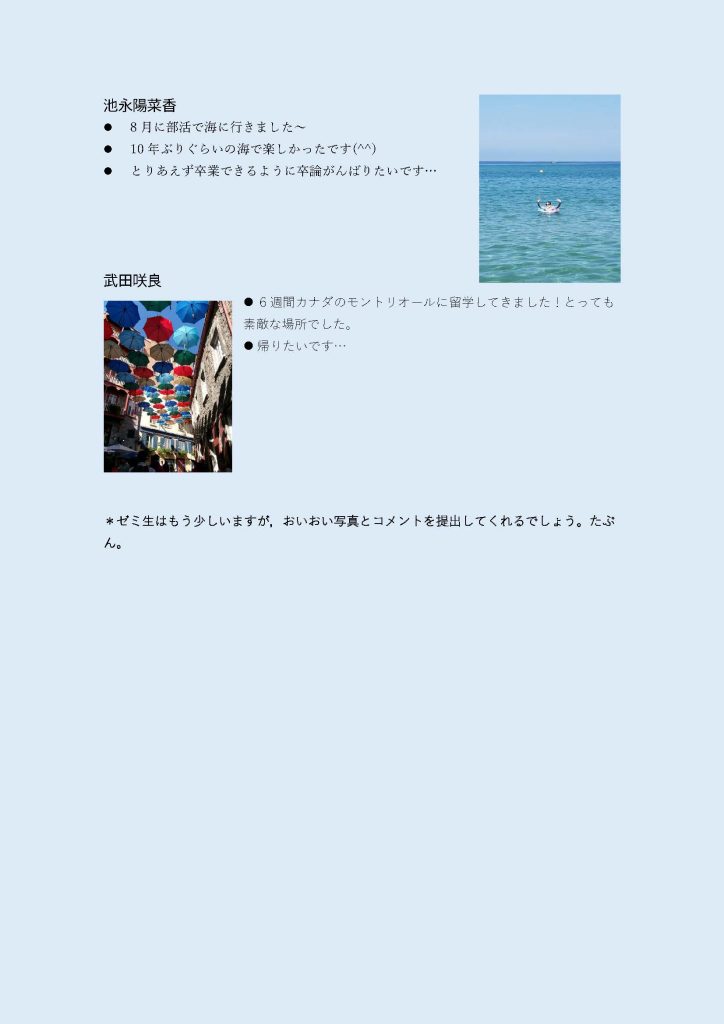
内田科研・森田科研共済の第1回 語彙・コロケーション研究会を2024年12月14日にJR博多シティ9F会議室4にて開催します。対面のみの開催です。また,会場の都合で先着20名までの受付とさせていただきます。
プログラムや詳細はこちらからご確認ください。
懇親会につきましては,予定しておりません。
ご質問やキャンセルのご連絡は,morita(a)hiroshima-cu.ac.jpまでお願いいたします((a)は@に変更してください)
阿部幸大 (2024)『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』光文社
ここ数年,アカデミック・ライティングの本を積極的に読んでいるが,この本は秀逸。巷の類書が,結局のところ本当には書き方を教えてくれていないということに気が付く。例えば,アーギュメントは単なる思いつきではなくて,「論証の必要な主張」である,と普通の本ならここで終わるが,本書では,この論証は具体的にどのようなものかをアーギュメントを鍛える過程でしめしている。抽象的な概念の導入から,具体的な方法論に落とし込んでいくという書き方自体が,アカデミック・ライティングそのものであるので,このような説明を読むことで,自ずと書き方を学んでいる。
これまでの概念を定義づけ,それを具体的な形に落とし込む方法を取りながらも,これまでの概念を疑い,批判的に見る方法も示してくれる。例えば,パラグラフ・ライティングにおいてどのような本でも説明される1つのパラグラフには,1つのトピックというルールは丁寧に説明される。通常は,そのトピックを論理的にサポートするという形式になるのだが,本書では,アーギュメントが論理的な飛躍をするために,その飛躍を埋めるために,文が連なると考えるのである。この考え方は,なぜ,論理的にサポートする必要があるのかを明確に示してくれる点で,これまでの類書の説明と大きく異なる。
論文は論理立てて説明されるだけでは書けるようにはならない。特に初学者は,何をどの程度書いて良いのかわからないため,逆に論文が短くなりがちということもある。論文として適切な長さ(の目安)の見つけ方,詳細な情報の提供方法などを通して,これまで暗示的に示された事柄について,具体的に明示的に示されるのは,論文を書くうえで大きなヒントになるだろう。
とベタ褒めしているが,コンパクトに,分かりやすくまとまっているが故に,注意が必要な点もある。まず,基本的には大学院生レベル,研究者レベルで読むと良く,それも人文系論文を書く際に役立つ。学部生だと厳しいかな,と感じる要因は,そもそも論文に触れている量が少ないため,説明が腑に落ちにくいのではないかと感じたからである。同様に,詳しく説明がなされるのは論文のイントロであるため,その他の箇所について他の本などを参照する必要がある。
学部生がレポートを書くなら,戸田山和久の『最新版 論文の教室: レポートから卒論まで』をまずは参照してほしい。また,パラグラフの書き方を日本語で学ぶなら松浦年男・田村早苗の『日本語パラグラフ・ライティング入門: 読み手を迷わせないための書く技術』がおすすめである。これらの本を読んだ上で,論文を読み,自分で書くと,よほど本書の言わんとすることが腑に落ちるのではないだろうか。